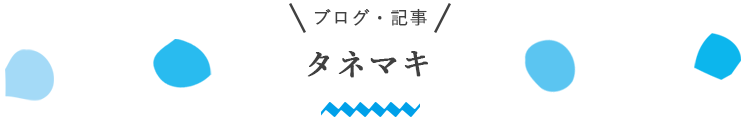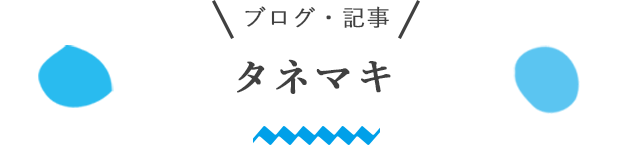1950年、徳島県に生まれた松本明生さんはいわゆる “団塊の世代”。高校を卒業し、法学を学ぶため、神戸大学の夜間部に進学しました。 松本さんとおよそ30年にわたり苦楽を共にしたパートナーの吉川恵さんは、こう振り返ります。
「当時はちょうど学生運動が盛んな頃。学生自治会の活動に関わったり、本を読むのに多くの時間を費やしたと聞きました。松本って本当は、とても寡黙な人なんです。最期に、自分のことを“クズの思想家”って言っていたけど、 思えば20代の頃から、“考えることが生きていくこと”という感じだったんだと思います」。


学生運動が下火になると、他の仲間同様に、情熱を傾ける対象を探しはじめた松本さん。一時は、仲間とともに農業に挑戦した時期もあったといいますが、それも長くは続きませんでした。なにか、を探して試行錯誤をつづけていた松本さんの心身にあるとき、異変がありました。

「たぶんその頃のことだと思うけど、目の前が灰色になった時期があるんですって。世の中が全部灰色に見えて、このままじゃ死んじゃうかもしれないと思ったって。それで、目の前にある山にひたすら登りつづけたらしいんです。そこで何かがストンと落ちて、やっと世の中に色がついた、なんてことをよく言っていましたね」と、恵さん。
日本が激動を遂げた戦後〜高度経済成長期に少年・青春時代を過ごした松本さん。さまざまな思考を巡らせるなかで原点回帰をし、たどり着いたのが、“生きることは食べること”という考えだったのでしょう。

「水と、光と、空気の次になくてはならないもの。それが、塩かなと思いました。でも、当時はまだ塩の専売法があって、塩の製造過程が見えない状態になっていたんです。塩屋になろうと思ってはいなかったけれど、個人でできる塩づくりを残しておくべきだと感じました」(2015年の取材より)。
ときは、1980年代後半。電気と機械を用いた効率的な製塩技術が確立し、国内の塩田はすべて姿を消していました。流通するのは工場でつくられた、ナトリウム純度の高い塩のみ。製造工程が見えないこと、食品としての塩の選択肢が1つしかなくなっていること、そしてそれが、“国によって制度化されている”ということにも疑問を覚えた松本さんは、製塩手法を学ぶため、伊豆大島へ赴きました。
(その3へつづく)
(その1はこちら→◎)